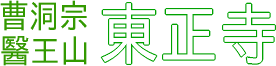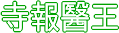伝道掲示板
なに一つ持たずに 生まれ出て
なに一つ持たずに 死んでいく
自分の物だと
りきんでいるが
みんな借り物 なにもない
俊也和尚の折々の法話4
北海道幌泉郡えりも町本町23
法光寺住職 佐野 俊也
この夏4年ぶりで家族と共に帰省しましたが、両親が不仲のようです。食事は別々、洗濯も各々で会話もほとんどありません。孫がいる間は居間で2人ともくつろいでいましたが、孫が寝ると別々の部屋にこもってしまいます。どちらかの味方をすればどちらかの機嫌を損なうので、どう接すれば良いかわかりません。周りには親類縁者もなく、子どもも私一人だけなので、今後のことが心配です。(50代・男性)
両親の心の声を「聴く」こと
地方の過疎化が進み、高齢のご夫妻が、寂しくお暮しになる様子が浮かびます。どちらかといえば元々寡黙な方々かも知れませんが、食事、洗濯も別々というのは、やや深刻な感じがします。健康状態はいかがなのでしょうか。
高齢になると、体力や気力の衰え、身体的な変化や認知機能の低下が見られます。これらの変化が、夫婦間の意見の食い違いや誤解、けんかの原因になります。また、友人や親しい方々との交流が減ると、互いに対する依存度が高まり、夫婦間の摩擦を生むことも多いようです。
相談者さんは、「母親とは季節の節目に話をして、何となく不仲について聞いていた」ということですが、母上は、遠慮して控えめに話をしていたのではないですか。本気で心配されるなら、度々電話をして様子を伺うことです。「どちらかの味方をすれば、機嫌を損なう」とありますが、母上はもっと頻繁に話をしたいのではないでしょうか。実際に親から片方の悪口や愚痴を聞くのは気が重い部分もあるでしょうが「聴く」ことによって、お二人の心身の状態も伺えると思います。父上との電話は難しそうですが、母上のお話を全部うのみにするのではなく、夫婦の関係性の変化を想像しながら、お二人の心の声を聴くことに努めるのです。
私は3年前の夏に父を、今年の1月には母を見送りました。父は行年97歳、母は95歳。父は、お世話になっていたお檀家様に伺い、命日の経をつとめ上機嫌で帰った翌朝、突然倒れて息を引きとりました。母は正月三日、箱根駅伝を見て父の母校の駒澤大学が優勝したのを喜び、カラオケを部屋で楽しんだ次の朝、黄泉の旅に上りました。どちらも長く入院することもなく、長寿を全うした後の呆気(あっけ)ない最期。町の皆様には、大往生と言って頂きましたが、一人息子の私にはいささか悔いが残りました。父はおしゃべり好きでしたが、晩年は毎度同じような話。私は「その話は聞き飽きたよ」と幾度か遮りました。その時の寂しそうな顔を、時々思い出します。父亡きあと母には、幾分認知症の兆候が見え始めましたが「まだ大丈夫」と思い、対応が幾分遅れた気がして、後悔が残りました。
一人息子の相談者さん。あなたのご両親はお元気そうですが、先の事はわかりません。あなたを産んで育ててくれた両親を、どうぞしっかりと見守って下さい。私からのお願いです。
「船橋よみうり新聞 土曜版」に月一回(第三土曜日)連載中です。

札幌市中央寺様での講話 若い方々に1時間のお話をつとめました。

皆さん背筋をのばして、お聴き頂いたようです。
トピックス
戦役殉難者精霊供養
慰霊法要を15日午前9時より、東正寺本堂に於て、東正寺梅花講員さんらと共に厳修し、百四十九柱のご冥福を祈った。
終戦から718年、今日私たちが日々豊かな暮らしを享受している平和と繁栄は戦禍の中で尊い命を捧げられた戦没者の皆様の重い犠牲の上に築き上げられてきたことを忘れることのないように。
また、世界の恒久平和への願いを込めて。
参列者0名。講員さん8名。

仏教のまめ知識
- お寺に魚がいる?
- お寺の本堂にはお経の拍子を取る木魚があります。また、修行道場には木製の大きな魚(魚鼓ほう)が吊り下げてあります。これは食事等の合図に用います。東正寺の坐禅堂には木製の小さな魚(魚鼓ほう)を吊しています。
なぜお寺に魚が?と思われるかも知れません。昔の人は「魚は眠らない」ものと思っていました。(実際は眠るようです、まぶたがないので目は閉じませんが)ですから、昼夜目を閉じない魚は不眠不休を表し、「魚のように昼夜の別なく寝る間を惜しんで、日夜修行に励むように」という修行僧への戒めとして魚鼓・木魚を打すということです。
お寺にお参りの際は木魚をよくご覧下さい。2匹の龍が両方から1つの玉(煩悩を表す)をくわえている形で、他は魚の鱗が彫ってあります(龍頭魚身りゅうとうぎょしん)。「魚が化して龍となる」登竜門の故事によるとの説があります。
中はくり抜いてあって空洞ですので音響効果がよく心地よい音色がします。
木魚は高価なものですので、叩きたいときは和尚さんの許可をもらってからにしてください。
感謝録&醫王縁助金
寄附単(感謝緑)
徳潤千祥居士三回忌供養
一、金参萬圓也 施主 尾地 良子様
良照竹泉大姉十三回忌供養
一、金弐萬圓也 施主 浜田 新一様
慈光克念居士十七回忌供養
一、金伍萬圓也 施主 匿 名様
報恩感謝
一、B5用紙千枚 施主 井上 忠子様
一、東側駐車場一面に砂利石敷き 施主(株)ユウテック様
ご寄附を頂き有り難うございます。
醫王縁助金
一金壱萬圓也 匿 名様 福島市
一金壱阡伍百圓也 匿 名様 新宮市
一金参阡圓也 加藤 寬治様 名古屋市
一金壱萬圓也 中谷 清美様 紀宝町
ご縁を助けて頂き有り難うございます。
国際ボランティアの寺
東正寺は、社団法人シャンティ国際ボランティア会(SVA)に登録した「国際ボランティアの寺」として活動しています。
ご協力の程 宜しくお願いします。
ほほえみ募金
募金箱は本堂に置いています。
令和5年11月28日現在 金80,372円
ほほえみ募金 → SVA → カンボジア・タイ・ラオス等の教育関係へ
◎SVAに寄託した募金額 金730,000円
アジアの図書館サポーター
アジアの図書館サポーターとして年間24,000円をSVAを通して支援しています。 この支援により、アジアでの図書館運営、移動図書館、図書館員の育成を支えています。(平成17年6月~継続)
絵本を届ける運動(カンボジア・ラオス)
1冊の絵本に、翻訳シールを貼りつける作業。
1組2,500円。過去275組送付。
絵本を届ける運動 (シャンティ国際ボランティア会)
回収
☆牛乳パック(切り開き、乾かして)
☆書き損じはがき・各種プリペイドカード
☆使用済み切手(切手のまわり1cm程度余白を残して封筒ごと切り取って下さい)
報告
10月29日から11月28日までに協力を頂いている方々です。
■使用済み切手
匿名様 セレモニーホール絆(堀口様)
加藤寬治様
ご協力ありがとうございます。
行事報告
せいゆうの行事報告
- 10日
- 保護司活動 街頭キャンペーン
- 15日
- 戦没者慰霊祭
智博
- 1日・16日
- 熊野病院ディ・ケア クラシックギター講師
- 7日
- 梅花本庁講習(東京都港区)
- 9日・10日(1泊2日)
- 人権擁護委員研修旅行 京都市人権資料展示施設・ツラッチティ千本
- 13日
- うどのまつり実行委員会 鵜殿交流センター
- 16日
- 梅花特別講習会(南泉寺) 講師 近藤如生師範
- 24日
- 人権擁護委員会議 第2回南牟婁地区部会 御浜町役場
- 26日
- 第47回東海管区曹洞宗青年会大会
三重曹洞宗青年会6周年記念大会
三重県文化会館 中ホール - 29日
- 梅の会(梅花講習)宗務所(松阪市)
- 毎土曜
- 東正寺梅花講講師
- 随時
- 東正寺・龍光寺梅花講若手対象の講師
智博&道雄
- 2日
- 第二宗務所青年会執行部会 南泉寺(熊野市有馬町)
- 14日
- 大仙寺晋山式準備(熊野市新鹿町)
- 15日
- 戦没者慰霊祭
- 30日
- 大仙寺晋山式準備
道雄
- 23日・24日(1泊2日)
- 比叡山延暦寺・竹生島宝厳寺参拝 ~彦根城見学
- 27日~29日
- 大仙寺晋山式準備
- 随時
- 龍光寺梅花講講師・境内清掃
- 随時
- 紀宝柔道会 幼・小・中学生指導
明美
- 随時
- 境内植木剪定・墓地清掃作業中
龍光寺本堂&トイレ清掃
友美
- 11日
- 大仙寺晋山式スナップ写真撮影打合せ
- 18日
- 新宮市なぎ看護学校でTeam雅の演舞
せいゆうのひとりごと
- PART ONE
- 3日、健志君の応援で、第43回三重県高等学校野球1年生大会(準々決勝)津商対津田学園の試合を観戦に豊里球場(津市高野尾町)まで行って来ました。試合結果は、12対8で津商が勝ち、準決勝(対三重高)に駒を進めました。健志君はキャッチャーで1年生の主将のようです。
妻と2人野球観戦で1日を過ごし、暫しの休息、気分転換になりました。 - PART TWO
- 5日、内閣府共催(全国10ヶ所で実施)の津波・避難訓練が午前9時から行われ、明美・友美・陽眞が参加しました。
- PART THREE
- 10日、保護司の活動として「子ども・若者育成支援協調月間」との連携による“社会を明るくする運動”街頭啓発活動と、熊野地区薬物乱用防止指導員として「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」の街頭キャンペーンを午後4時から主婦の店パシフィックマーケット店舗前で行いました。
この“社会を明るくする運動”を思う時、10月8日に他界された音楽家の谷村新司氏を思います。谷村氏は、この運動のフラッグアーティスト(運動の旗振り役)に就任されており、“社会を明るくする運動”の応援ソング「咲きほこる花のように」を作詞作曲されています。
平成21年の広報ポスターや平成24年のCM動画への出演、又、その後、更生保護施設や社会貢献活動場所などを訪問し、実際に立ち直ろうと頑張っている人々や現場で活躍する更生保護ボランティアの人々と、音楽を通して触れ合うう企画“こころをつなぐプロジェクト”を行っていました。
学生時代「アリス」の曲をよく聴き歌いました。その一員の谷村氏が“社会を明るくする運動”の旗振り役として活動されていた事が、私にとっても励みになっています。 - PART FOUR
- 16日、梅花本庁講習講師の特別講習会(講師・広島県済法寺住職 近藤如生師範)が南泉寺(熊野市有馬町)に於いて開催され、午前中は講員さん対象で、龍光寺3名・東正寺1名受講。午後は、寺族・師範対象で明美が受講。智博は、午前午後、少しの時間ですが檀務等の合間をぬって受講しました。
道雄は、檀務が忙しく残念ながら受講出来ませんでした。
今回、南泉寺主催の講習会でしたが、東正寺でも機会があれば開催したいと思っています。
東正寺梅花講は、ベテラン組(8名)が毎週土曜日の午後1時半から3時まで。若手(3名)は不定期ですが、午後6時から8時まで智博の指導を受けています。
因みに、龍光寺梅花講は、ベテラン組(3名)が不定期ですが、午前9時から11時まで道雄の指導を受けています。若手(3名)も不定期ですが、午後6時半から8時まで智博の指導を受けています。
梅花を習いたい方、遠慮無くご相談下さい。 - PART FIVE
- 19日、智博と友美は、天空ハーフマラソン(新宮・那智勝浦)を出走、智博ハーフ(1時間59分)、友美3キロ(22分)。
- PART SIX
- 23日、智博と友美は、うどのまつりに参加。陽眞も明美と一緒に神輿の後を追いました。4年振りの楽しい1日となりました。


お寺からのお願い
位牌堂の照明スイッチについて
これまでは、位牌堂右手にあるスイッチを利用して頂いてましたが、「感知式」にしましたので、そのまま位牌の前にお進みお参り下さい。約5分間点灯します。
位牌堂の奥が、開山堂です。
写真は、平成27(2015)年9月10日に落慶式を終えた開山堂です。
道元禅師様(右)永平寺開山
瑩山禅師様(左)總持寺開山

ゴミについて
平成15(2003)年4月より、試行錯誤しながら墓地のゴミ処理に取り組んでいます。
ゴミ(しきみ・色花・草等)を持ち帰ることのできる方は、ご協力をお願いします。
墓地掃除を請け負っている方は、請け負っている方の責任において持ち帰って処理して下さい。
ゴミを山に捨てないで下さい。
次の物は、必ず持ち帰り下さい。
- 墓地で使用した、タワシ・雑巾・手袋
- お供え物(果物・お菓子類・酒瓶・ビール缶・ジュース缶・セトモノ等)
- ポリバケツや個人名を書いているバケツ
尚、古い塔婆は、山門前バケツ置き場横の小屋(古い塔婆入れ)に置いて下さい。
神棚と仏壇
人が亡くなりお家に伺いますと、神棚が閉じられていますが、仏壇も閉じられている場合も見受けられます。
人が亡くなるとお家の神棚を白い半紙などで閉じます。そして49日の法要が済んでから取り除き神棚の祀りを再開します。これを「神棚封じ」と言い、神様の住む聖なる場所である神棚に死忌が及ばないように封印するものです。
その際、仏壇を閉めるのは間違いです。「神棚を閉じる」ことと「仏壇を閉じる」ことを混同している方がいるようです。忌中の間もお仏壇のご本尊さま、ご先祖さまには香華灯燭仏飯をお供えします。そしていつものように毎日礼拝を続け、亡き人を一刻も早くみ仏の浄土へとお導き頂けるように祈願いたします。
続・夢積み立て 庫裡台所等々の改築工事
一、金壱阡圓也 写経奉納金
一、金壱阡圓也 寒修行托鉢浄財追加
一、金参圓也 預金利息
一、金壱萬圓也 施主 片野 晴友(通算 金十二万円也)
令和4年12月28日から令和5年11月28日現在
目標金額 住職私案 2,000万円
積立金額 金798,503円
内訳
写経奉納金累計額 金31,000円
寒修行托鉢浄財金累計額 金588,934円
喜捨累計額 金178,553円
預金利息累計額 金16円
喜捨金(寄附金)につきましては、鐘楼堂(平成7年)・山門(平成12年)・坐禅堂(平成23年)・開山堂(平成27年)の建立時、又本堂樋取替と本堂外壁塗装工事費(令和4年)と同様に、気になる方は気がむきましたら、無理のない喜捨をして下さい。たとえば
・「生きていてよかった」という何かいいことがあって。
・その時、運良くお金がいっぱいあって
・気持ちよく人に与えたい。
自然にこんな気持ちになった時で結構ですという考えで続けています。
今月の坐禅
安泰寺では、1年間1800時間の坐禅ができるという。
私はどれくらい坐れるだろうか。
11月の坐禅の時間・・・590分
トータル・・・6802分(113時間22分)
参加してみませんか?
坐禅会

- 東正寺朝の坐禅会
- 場所 東正寺坐禅堂&本堂
日 毎月18日
時 午前5時~午前6時
坐禅堂で30分の坐禅の後、本堂においてお経(般若心経・大悲心陀羅尼・舎利礼文)を読誦。
坐ってみたい方 遠慮なく来てください。 - 臘八摂心会
- 場所 坐禅堂
日 12月1日~8日
時 午前5時半~午前6時半 - 東正寺夜の坐禅会(不定期)
- 場所 東正寺坐禅堂&本堂
日 12月7日 19時~20時 - 11月の坐禅会の参禅者
- 東正寺朝の部 18日 7名
東正寺夜の部 16日 4名
夜の部の坐禅について
| 令和5年日程 | 12月7日(木) |
|---|---|
| 時間 | 午後7時~午後8時 |
| 場所 | 坐禅堂&本堂 |
| 内容 | 坐禅(30分)・お経・お茶 坐禅堂で30分の坐禅の後、本堂にてお茶。 |
- 19時より本堂にて座り方の説明をしたのち、坐禅堂に移動します。
- 日時は変更になる場合もございます。
- 参加される方は、坐禅のしやすい服装(ジャージ等)でお越し下さい。
- 足が組めない方には椅子を使った坐禅をご指導させていただきます。
- 事前に申し込みはいりません。直接お寺にお越し下さい。
夜の部の坐禅会をお知らせするLINEアカウントを作成しました

LINEアプリの友だちタブを開き、画面右上にある友だち追加ボタン>[QRコード]をタップして、コードリーダーでスキャンしてください。
https://line.me/R/ti/p/@400vqzmt
夜の部の坐禅会の前日にお知らせメッセージを送信します。
QRコードを読み取り、お友だち追加よろしくお願いします。
写経会
写経室(坐禅堂1階)において、
毎日 午前中(午前8時~正午)に各自行う事が出来ます。
受付 午前8時~午前11時まで庫裡玄関にて受け付けます。
写経用紙・筆ペンは、用意しています。奉納金は、一部1,000円です。
(奉納金は、本堂トユ取替と本堂外壁塗装工事費として積み立てます)
日曜学校
毎週日曜日
午前7時~午前8時
内容 ラジオ体操・坐禅・お経・掃除・お茶
対象は小学生・中学生です。本人が希望すれば幼稚園児・高校生・18歳未満まで可。
上記の他にも、花まつり・遠足・田植え・収穫祭・忘年会等の催しがあります。
詳しくは日曜学校のページをご覧下さい。